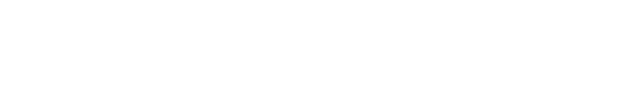腎臓病でも食べてもいい野菜や果物について
こんにちは、じんぞうの学校の校長で腎臓専門医の森 維久郎です。
この記事では腎臓病の患者さんにとって一番悩みの食事の治療について触れたいと思います。
日々診療をしていると、インターネットで調べてみると、あれも食べちゃダメ、これも食べちゃダメと書かれており、じゃぁ一体何を食べたらよいと悩まれている方が多いように感じます。
そして不必要な食事制限をしていたり、我流の間違った食事療法を選択している人が非常に多いと感じています。
腎臓学会が発行するガイドラインでも軽症である慢性腎臓病ステージ3a(腎臓病の方の6-7割がステージ3a)の方にはカリウム制限は推奨されておりません。
この記事では本当に必要な方はだれか、そして特に注意が必要な食べ物について触れたいと思います。
まず最初に読んでほしいこと
腎機能が低下していると、時に野菜・果物の制限が必要になることがあります。
ただし、腎機能が低下していると、たんぱく質や、塩分の制限も必要になることが多く、何を食べたらよいか分からないという声を聞きます。
野菜・果物の中でも、食べない方が良いものと、比較的に食べても大丈夫なものがあります。
ただし、食べて良いかどうかは患者さんの腎機能の状態によって異なるので最終的に主治医と相談をしてください。
全ての腎臓病の患者さんに制限はいらない
野菜・果物に含まれるカリウムが上がると突然死する不整脈を起こすため、我々医師側も腎機能が低下している患者さんの診療では食べている野菜・果物の量が気になります。
しかし、日本で現在、腎臓病と言われる腎機能が低下している方は1300万人もいて、全ての患者さんが野菜や果物を制限する必要はありません。
事実腎臓学会が発行するガイドラインでも軽症である慢性腎臓病ステージ3a(腎臓病の方の6-7割がステージ3a)の方にはカリウム制限は推奨されておりません。
腎臓病には様々なタイプの腎臓病があり、以下の要因によってカリウムの溜まりやすさが異なるためしっかり採血をしながら制限が必要かを考える必要があります。
- 腎機能が低下する原因の病気
- 薬の影響
- 腎機能低下の重症度 など
何故、野菜や果物を制限するのか
腎機能が低下した場合、例えば、血液透析になる直前の患者さんでは野菜や果物を含まれている『カリウム』という物質が、尿で排泄されなくなり、身体に溜まってしまいます。
この状態は高カリウム血症と言い、カリウムの値が5.5以上になると、突然死の原因となる不整脈が起きる可能性があるため注意が必要です。
患者さんによって、食べて良いかが異なると先ほど伝えましたが、「カリウムが5.5以上になる可能性が高い場合」は野菜・果物をひかえる必要があります。
野菜・果物と腎臓病(ベジタリアンの例から)
ベジタリアンと腎臓の相性はあまり良くないんじゃないかと言われていました。
野菜や果物に含まれる植物性蛋白や鉄分は腸での吸収の効率が悪く、その割にカリウムが含まれるのでベジタリアンは腎機能の視点から健康被害があるのではないかと考えられていたようです。
しかしながら、複数の長年の観察した研究結果から、肉食とベジタリアンを比較した場合、ベジタリアンの方が臨床経過が良いのではないかという報告や腎臓病で植物性蛋白をとっている割合が多い人の方が死亡率が低いという結果があるようです。(*1)
逆に、赤身を多く食べる患者の方が腎臓に良くないのではないかという研究結果も出ています。(*2)
その他、ビタミンC、ビタミンEの抗酸化作用は微量ながらも腎保護的に働く可能性があること、食物繊維が、癌の抑制や血糖のコントロールを良くする効果があることから最近では野菜・果物については見直しが行われています。
*1 Am J Kidney Dis. 2016 Mar;67(3):423-30.
*2 J Am Soc Nephrol. 2017 Jan;28(1):304-312.
野菜と果物は腎臓に良いのか
腎機能低下が起きていると目の敵にされる野菜と果物ですが、視点を変えると腎臓にとって肯定的にとらえることも可能です。
血圧を下げる
例えば、野菜と果物に含まれるカリウムは血圧を下げる効果があります。血圧を下げることは腎臓にとって良いです。(*1)
不飽和脂肪酸が血糖を下げる
植物に含まれている脂質は不飽和脂肪酸といい、肉などに含まれる飽和脂肪酸を摂るのと比較して糖尿病による腎障害を抑える可能性や生命予後を良くする報告もあります。
体が酸性になるのを防ぐ
腎機能が低下すると、体が酸性になり、酸性になると腎機能の低下が進みます。その際に重曹と呼ばれる体をアルカリにする薬を使用しますが、野菜・果物でも同様の効果が得られると報告されています。(*2)
*1 高血圧ガイドライン2020
*2 エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2018
腎臓病で食べない方が良い野菜・果物
アメリカの科学誌から、腎機能が低下している患者さんで避けるべき食材として「一部の野菜・果物、加工食品、肉、乳製品」などが挙げられています。
一部の野菜・果物として、以下の3つはカリウムの吸収が良いため控えるように書かれています。
- ジュース
- ベジタブルソース
- ドライフルーツ
加えて、臨床家の中ではイモ類でカリウムが上がることが経験として共有されており、自分の診療でも注意するように伝えています。
- イモ類
一方で、葉物などはあまりカリウムが上がらないので透析直前の重症の患者さんでは制限していますが、軽症~中等症の患者さんでは制限が不要なことが多いです。
ただ結局、個人差も結構大きいので、最終的には血液検査でカリウムを測定しながら必要性を見極めています。
*1 Plant-Based Diets for Kidney Disease: A Guide for Clinicians
カリウムを下げる薬を飲みながらしっかり食事をとる(私見)
これはあくまで私見ですが、野菜・果物を制限したり茹でこぼしたりすることで大切な栄養素が抜けてしまうので、患者さんによって食事をしっかりとりながらカリウムを下げる薬を飲むことを勧めています。
2020年にカリウムを下げる効果の高い「ロケルマ」という薬が出ました。
この薬のおかげで、自分が診察している患者さんの大半で野菜・果物の制限が不要になりました。
実際、腎機能が低下した患者さんで、ロケルマを使用したところ、投薬制限なし・食事制限なしで1年間カリウムの値を5.5以下に保つことができたという報告があります。(*1)
*1 Sodium Zirconium Cyclosilicate among Individuals with Hyperkalemia(CJASN)
ただしこの薬はかなり高価なので、金銭的に負担になる方も多くいらっしゃいます。
またこの考え方個人的な意見で、医師によって治療方針が変わるので主治医の先生としっかり相談をしてください。
腎臓の食事でお悩みの方へ
いかがでしたでしょうか?
腎臓病になると野菜・果物を控えましょうと言われますが、検査データーを見比べながら食べてよいもの・食べていけないものをしっかり把握していくと良いです。
腎臓の食事と言われるとあれもだめ、これもだめと悩んでいる腎臓病の患者さんを多くみかけます。
じんぞうの学校では腎臓の患者さん向けの情報配信を
- Youtubeチャンネル
- 専門医監修のレシピ集
- 栄養コラム など
で積極的に行っております。
youtubeチャンネル
youtubeチャンネルで配信している動画の一部を貼っておきます。
この他にも、カリウム、タンパク質の食べ方の基本的な所から、この食材がお勧めという具体的な話まで触れていきます。
また食事だけでなく
- 腎臓専門医の医学講座
- 近年話題の腎臓リハビリテーション
についての動画も作成しているので是非チャンネル登録をお願いします!
レシピ集
じんぞうの学校を運営している赤羽もり内科・腎臓内科ではレシピ集を書籍「腎臓病とわかったら最初に読む食事の本(無理なく続けられる満足レシピ)」として出版をしております。
レシピを紹介するだけでなく、腎臓病の食事療法に取り組む上で必ず知っておいて欲しい内容をなるべくかみ砕いてお伝えしております。
栄養コラム
身近の食品について質問があるものに触れています。
良かったご参考ください。
【じんぞうの学校について】
【基礎知識】
【食事療法総論】
【食事療法各論】
【コラム】